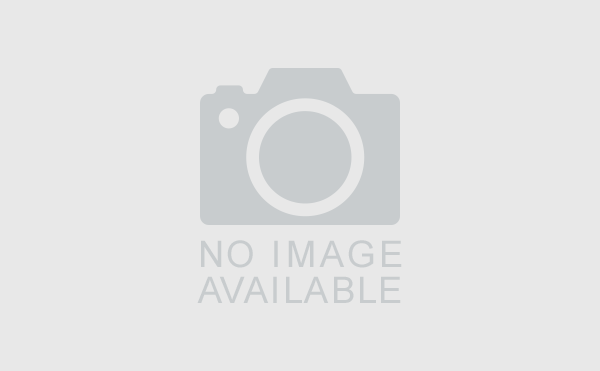犬の糖尿病の治療管理
糖尿病の確定診断
特徴的な多飲、多尿、体重減少、空腹時高血糖、尿糖陽性が認められれば糖尿病と診断してよい。その後に、基礎疾患の有無について検査する。
高血糖が2週間以上続くと糖毒性で細胞が破壊されるので、犬を糖尿病と診断したらすぐにインスリン治療。
糖尿病治療の目標はQOLの改善であり、具体的には体重維持、多飲・多尿の改善、合併症(白内障、網膜症、腎症など)の予防である。
糖尿病を理解するための基礎知識
血糖の調節は膵臓の内分泌ホルモンのインスリン(下降)とグルカゴン(上昇)による
Ⅰ型糖尿病(インスリンが作れない)
犬はインスリン分泌無しが多い(膵島β細胞の空胞変性や免疫介在性膵島炎,自己免疫疾患)。
Ⅱ型糖尿病(インスリンの不足、インスリン抵抗性)
インスリン抵抗性(インスリンが足りていても細胞が取り込めない)
黄体から分泌されるプロゲステロンが強力なインスリン抵抗性を引き起こす。
成長ホルモンによるインスリン抵抗性はきわめて強力である。
グルコース毒性(血糖の状態が長期間続くと,インスリン生合成の低下を伴う膵β細胞機能障害および膵β細胞数の減少が徐々に誘発され,インスリン分泌が低下して,さらなる高血糖を導くという悪循環に陥る。)
ソモギー効果(インスリンの投与後に血糖値が低くなりすぎることで血糖値を上げるためのグルカゴン、カテコールアミン、コルチコステロイドなどが分泌されて起こる血糖値のリバウンド現象。)
糖化アルブミン(持続的な高血糖により血清アルブミンが糖修飾をうけたもの、過去2週間程度の血糖値を反映する。)
インスリン治療の要点
インスリン注射後に血糖値がゆるやかに下降し、5~7時間程度で極小を示し、次第に投与前値に復帰するのが望ましい。
1日を通して血糖値が100~250mg/dLの範囲に入っているのが理想
インスリンを過剰に投与すると低血糖の危険がある。
低血糖による血糖上昇ホルモンは強いインスリン抵抗性をもつため、その後約1日はインスリンを投与しても血糖は降下しなくなる。
インスリンの1回投与量が1.5U/kgを越えても血糖が降下しなければ、重篤なインスリン抵抗性と判断し、併発疾患(クッシング症候群など)を再検討する。
初期用量 0.25-0.5 U/kg BID
インスリンの分類
短時間作用型:レギュラーインスリン(一般にR)(商品名ヒューマリンR,ノボリンR)
中時間作用型:NPHインスリン(一般にN)(商品名ヒューマリンN、ノボリンN)
中時間作用型:レンテインスリン(一般にL)
長時間作用型:ウルトラレンテインスリン(一般にU)およびPZIインスリン
インスリングラルギン(商品名ランタス)
デテミル(レベミル)作用時間はランタスとNPHの中間程度
これらを単剤または組み合わせて使用することで、糖尿病の犬のほとんどに対応できる。
一般に、小型犬では皮下投与したインスリンの作用時間が短く、大型犬では長い。このため小型犬では作用時間の長いインスリン、大型犬では作用時間が比較的短いインスリンを使用する。
インスリン製剤を生理食塩水で希釈すると一般に作用時間が短くなる。しかし、いったん希釈したインスリンの作用時間は安定している
インスリングラルギン(ランタスは特殊な緩衝液に溶解されており、希釈できない
血糖曲線測定が最良の目安
インスリン投与前、投与後3,6,9時間の血糖値を測定し、血糖曲線を引く。
初期の段階では、その犬におけるインスリン作用時間を知ることが重要である。理想的には、インスリン注射後に血糖値がゆるやかに下降し、5~7時間程度で極小を示し、次第に投与前値に復帰するのが望ましい。
インスリンの作用が短い場合には、より作用時間の長いインスリン製剤に変更する(例:NPH→インスリングラルギン。インスリンの作用が長すぎる場合には、より作用時間の短いインスリン製剤に変更する(場合によっては1日1回投与を試してみてもよい)。
使用するインスリン製剤が決まったら、投与前の血糖値と、極小の血糖値の差(インスリン作用の深さ)が200~250mg/dLとなるように、インスリン投与量を増減するインスリンを使用し始めたばかりの段階では、血糖値を正常範囲(100mg/dL)に近づけようとしてはならない!
インスリンを過剰に投与すると低血糖の危険がある。低血糖に陥った体内では、血糖値を上昇させるためにグルカゴン、グルココルチコイド、カテコラミンが分泌され、血糖値は急激に上昇する。
また、これらの血糖上昇ホルモンは強いインスリン抵抗性をもつため、その後約1日はインスリンを投与しても血糖は降下しなくなる。これを「ソモギー効果」という
反対に、血糖が降下しない場合には、インスリンの1回投与量を2~3割ずつ増やす。
インスリンの1回投与量が1.5U/kgを越えても血糖が降下しなければ、重篤なインスリン抵抗性と判断し、併発疾患(クッシング症候群など)を再検討する。
血糖曲線がちょうどよい状態になったら、その時点のインスリンを当面の投与量として、犬を帰宅させる。オーナーにはインスリン投与法、低血糖時の対応、自宅での尿糖検査を指導する。
維持治療とインスリン投与量の調節
初期治療で血糖値の底が高くても、しばらく投与しているうちに、血糖曲線は全体に降下する。これはインスリン投与によって「グルコース中毒」が解消されることによる。これを考慮せずに慌ててインスリンを増減してはいけない。これは血糖コントロールで最も陥りやすい失敗のひとつである。
治療開始後しばらくは1週間程度の間隔で再検査する。朝、普段通りの時間に食餌を与えてインスリン投与し、午後(血糖曲線が最低になる時間帯が望ましい)に来院してもらう。
来院時には動物の状態(飲水量、尿量、脱水の程度、体重)を観察し、血糖測定を行う。
体重はその犬種の理想体重に近づけるようにする。
血糖曲線の底が80~180mg/dLになることを目標にインスリン投与量を調節する。
できれば1日を通して血糖値が100~250mg/dLの範囲に入っているのが理想であり、糖尿碑病合併症を最低限に抑えることができるが、ここまでコントロールするのは非常に難しい。
インスリン減量
注射前血糖値180mg/dl以下インスリンを50%減量
インスリンを増量しても思ったようなコントロールができないときは、併発疾患を探すか、血糖曲線を書き直すほうが安全である。糖尿病を治療しているうちにインスリン感受性や作用時間が変化することもある。
血糖曲線を見れば、適宜インスリン製剤を変更する材料にもなる。インスリンをむやみに増量すると致死的な低血糖を起こす危険がある。
インスリン投与直後に急激な血糖降下が起こり、それに対する反応(ソモギー効果)によって検査時には高血糖になっていることもある。
作用時間のより長い製剤を併用すると、血糖曲線を平坦化しやすくなることが多い
長期管理
体重が安定し、尿糖が陰性~弱陽性であり、臨床症状が良好であれば、インスリン投与量をいったん固定して4~6週間ごとに定期検査する。
予後
犬の糖尿病の予後は血糖コントロールの程度や、基礎疾患・併発疾患の程度による。糖尿病そのものが死因になることはなく、心不全、肺炎、腎不
全、感染症、無関係の腫癌、老衰などが最終的な死因になる。
基礎疾患・併発疾患の診断
犬を糖尿病と診断したら、糖尿病の疾患分類のため、治療計画のため、あるいは予後判定のために基礎疾患・併発疾患の検査を見落とさないようにする。
糖尿病の基礎疾患
- クッシング症候群
- 膵炎
- 発情
- 卵胞嚢腫
- 黄体嚢腫
- 子宮蓄膿症
糖尿病の併発疾患
- 尿路感染症(勝脳炎、前立腺炎、腎炎)
- 慢性腎不全(腎症)
- 白内障
- ブドウ膜炎
- 網膜症
- 皮膚炎・皮膚感染症
- 脱毛
糖尿病治療の概要
犬では血糖コントロールを厳密にしても白内障や網膜症を防ぐのが難しい。
血糖コントロールが不良であれば、かなり早い時期に腎症(進行性の慢性腎不全)が問題となる。
たとえ臨床的な慢性腎不全が起こらなくても、病理組織学的には糸球体や近位尿細管の障害が進行しているので、糖尿病が犬の腎臓に与える影響を軽視してはいけない。
その他の合併症は短期~長期を通じてあまり問題にならない。
犬はインスリン分泌無しが多い(膵島β細胞の空胞変性や免疫介在性膵島炎,自己免疫疾患)。
雌犬の避妊の重要性(インスリン抵抗性の回避)
発情後には、黄体から分泌されるプロゲステロンが強力なインスリン抵抗性を引き起こす。
糖尿病の治療中に発情すると、血糖コントロールが著しく難しくなる。この状態は黄体が自然消退するまで1カ月以上も持続する。
糖尿病と診断した雌犬では、可能な限り卵巣(子宮卵巣)摘出術を行う。一過性の発情後高血糖であっても、将来(次回発情時)の再発や糖尿病移行を予防するためには手術するほうがよい。
ブロゲステロンが異所性の成長ホルモン分泌を起こすといわれている。成長ホルモンによるインスリン抵抗性はきわめて強力である。
その他の原因として、先天性の膵島形成不全によると思われる若年性糖尿病がしばしば認められる。