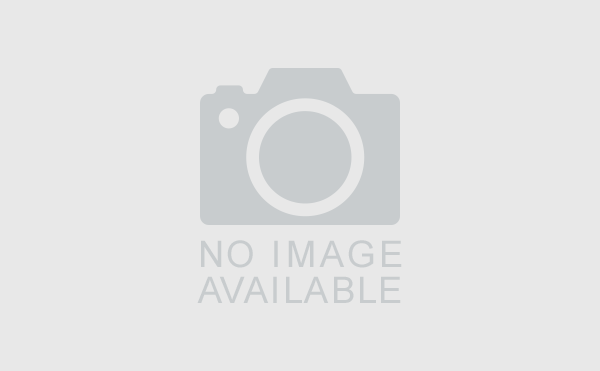グルココルチロイド
目次
グルココルチコイド抗炎症作用のメカニズム
リポコルチン(アネキシンA1)という抗炎症タンパク質の合成を促進、リポコルチンはホスホリパーゼA2を阻害することで、アラキドン酸カスケードを抑制し、プロスタグランジンやロイコトリエンなどの炎症メディエーターの産生を減少させる。
NF-κBやAP-1などの転写因子の活性を抑制することで、IL-1、IL-6、TNF-αなどの炎症性サイトカインの産生を減少させる。
好中球やマクロファージなどの炎症細胞の遊走や活性化を抑制し、血管透過性の亢進を抑えることで、炎症反応を総合的に抑制する。
NSAIDsはシクロオキシゲナーゼ酵素の阻害によりプロスタグランジン産生を抑制するのに対し,グ ルココルチコイ ドは炎症プロセスのもっと前の段階を抑制する。
グルココルチコイドの他の抗炎症作用は免疫抑制作用にオーバーラップする。
グルココルチコイドは細胞接着分子の膜圧を変化させ,白血球像の変化(血液中の成熟好中球の増加,リ ンパ球と好酸球減少,単球は不定性に増加)を引き起こす。
一般的に,グルココルチコイドはー単球の食作用とサイトカイン生産に対し,最も明確な免疫学的作用を示す。これらの作用は,有益(例:免 疫介在性溶血性貧血の治療)にも有害(例:真菌,ウ イルス,細 菌感染に対する防御の低下)にもなりうる。
猫は犬と違い,犬 同様の生物学的作用を示すにはより高用量(たいてい倍量)の グルココルチコイドを必要とする。これは,猫の細胞内グルココルチコイド受容体がより少なく感 受性が低いためと思われる。
グルココルチコイド作用の比較
ヒドロコルチゾン:プレドニゾロン:デキサメタゾン=1:4:25
V.M.November2002
PETER J. BONDY Jr, DVM
LEAH A. COHN, DVM, PhD, DACVIM
獣医師は個々の症例に適 した理論的なグルココルチコイ ド治療プログラムを計画するとき,診 断,グ ルココルチコイド療法の目的,治 療計画,入 手可能なグルココルチコイド製剤,そ して患者特有の因子などを考えなければならない。そして治療をモニターし副作用を減らす一方,効 果を維持するように常に調節していかなければならない。
グルココルチコイド療法の要約(chatGPT)
1. 補充療法(アジソン病など)
- 診断と初期対応:ACTH刺激試験により副腎皮質機能低下症を診断、生理食塩水と必要に応じてデキサメタゾンを投与。
- 長期管理:プレドニゾンなどを用い、ストレス時は一時的に投与量を増量。
2. 高用量短期療法
- 適応例:中枢神経外傷、アナフィラキシー、特定のショック(ただし敗血症性ショックには推奨されない)。
- 使用薬剤:主にメチルプレドニゾロンが使用され、デキサメタゾンよりも好まれることが多い。
3. 抗炎症療法
- 主な使用薬:プレドニゾン/プレドニゾロン(経口)、必要に応じて注射製剤。
- 注意点:感染の悪化に注意し、必要なら抗生物質と併用。中間型製剤が推奨される。
4. 免疫抑制療法
- 対象疾患:免疫介在性疾患(IMHA、ITP、SLEなど)。
- 投与量:犬では2–3mg/kg/日、猫では4–10mg/kg/日のプレドニゾロン。25kg以上の大型犬は体表面積で計算する
- 併用療法:副作用軽減のため他の免疫抑制剤と併用することも。
5. 抗腫瘍療法
- 適応例:リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫など。
- 注意点:診断前投与により診断困難になることがある。多剤耐性の懸念も。
6. 局所療法
- 部位別の使用法:
- 眼科:点眼や結膜下注射。ウイルス感染時は禁忌。
- 皮膚:局所製剤での治療が可能だが、長期使用で副作用の懸念。
- 呼吸器:吸入療法が補助的に使われる(例:猫喘息)。
- 消化器:直腸泡沫剤などが限定的に使用される。
- 関節:関節内注射はまれだが、待機的に行われることがある。
総合的な注意点:
- グルココルチコイドは即効性と多様な効果があるが、副作用(感染リスク、免疫抑制、内分泌抑制など)への注意が必要。
- 投与量は最小限に、可能なら段階的に減量・中止することが望ましい。
- 感染症との鑑別と管理が極めて重要。
全身性のグルココルチコイド療法
グ ルココルチコイド補充療法 アジソン病
まず副腎皮質機能低下症の確定診断をする。これはACTH刺激試験によって行われる。副腎皮質機能低下症が疑われる症例に対 しては生理食塩水の輸液療法を迅速に開始する。
診断のためのACTH刺激試験結果が数時間以上遅延した場合は,生理的な量のデキサメタゾンリン酸塩(0.1~0.2mg/kg,初回は静脈内投与)を追加投与すべきである。プレドニゾンとハイドロコルチゾンは内因性のコルチゾール測定に影響するので,ACTH刺激試験の前にこれらを投与するべきではない。
長期間のステロイド補充療法を始めると症例の状態は安定する。グルココルチコイド製剤のいくつかはミネラルコルチコイド作用を 有するが,通 常ミネラルコルチコイド補充には適さない。
選択され るグルココルチコイドは生物学的作用時間が約24時 間で,投与量は炎症抑 制量以下にすべ きである。プレドニゾンまたはプレドニ ゾロン(0 .2~0.3mg/kg,PO,1日1回)がこれに適して いる。移動や診断治療 に伴 うス トレスの持続に対しては,ど の ミネラルコルチ コイド製剤でも理的需要の増 加 に合 ように投与量を一時的 に増量する1)。 基本的にス トレス状態では1日 のグルココルチ コイ ド投与量を倍にする.
高用量による短期間の治療
早急な効果発現が望まれる中枢神経の外傷,ア ナフィラキシーにおいて,グルココルチコイドは短期間,多くの場合1回 だけの治療として高用量で使 われる。
脊髄に損傷を受けた動物は受傷後8時 間以内にコハク酸メチルプレドニゾ ロ ン ナ トリ ウ ム(SoluMedorolPharmacia&Upjohn:15~40mg/kg,IV)でれ ば効果的である2~5’8)。2~6時治療 をす間後 に15mg/kgのボー ラス投与を行 う。その後,7.5mg/kgを6時の ボーラス投与を24時間,または.5mg/kg/hrの間おき一 定量 の24時間静脈点滴を行う。
強い抗 酸化作用があり,また効果の持続時間が短いためにメチルプ レドニゾロンがデキサメ タゾンよりも好まれる。 しかし,たとえ受傷後す ぐであっても脳の外傷に対 してグルココルチコイ ドは推奨されない。
ショックの治療 に対する高用量のグル ココルチ コイ ドの投 与 は効果的であったりなかった りする。アナフイラキ シーシ ョックに対 してのみ高用量 のグルココルチコイドの使用が推奨 される13)。1970年 代 と1980年 代初頭 の文 献では,グ ル ココルチコイ ドが血圧上昇効果を持つために,出 血性ショックに対 し高用量投与 を推奨していた。しか し,グ ルココルチコイ ドのこの用法は効果的ではなく,そ の代わりの治療 として,血 液量の増加,コ ロイドとヘモグロビンの補充を目的とするべきである。
敗血症ショック時のグルココルチコイド治療の効果はいまだに賛否両論である。1970年 代の実験的な研究は短時間作用型のグルココルチコイ ドの高用量投与(30mg/kgメチルプレドニゾロン)は敗血症ショックによる病的状態を軽減するという理論を裏付けている。しか し,ヒ トでの臨床試験ではそのような結果は得られておらず,敗 血症時の高用量コルチコステロイド療法は推奨 されていない14)。最近,ヒ トにおいてグルココルチコイドは敗血症や敗血症ショックの治療に使われ始めているが,偽 副腎不全 を考慮して一般的な投与量より少ない量が投与されている。今までのところ,偽 副腎不全の発症は獣医領域の患者においては報告されておらず,動物の敗血症症例に対する低用量グルココルチコイドの治療効果は不明である。
短期間の高用量グルココルチコイド療法は,多 くの獣医師により大量のサイトカイン放出が予測される状態において行われている。例えば,胃 拡張捻転症候群,毒 蛇による咬傷,敗 血症時を除く全身性の炎症の場合である。
そのような症例における獣医療領域の臨床研究は報告されていない17-20)。証 拠 がないのは証拠がないという証拠ではないという格言があるが,これらの疾患における高用量グルココルチコイド療法を試すべきである。
出血性ショック時,敗血症性ショック時およびサイトカイン放出時にグルココルチコイ ド療法が効果的であるという動物の症例報告はないが,グ ルココルチコイド療法は効果的でないという根拠はない。それにもかかわらず,今のところ筆者らはこれらの状態における高用量グルココルチコイ ドを推奨していない。
抗炎症療法
理想的には根底にある炎症の原因を発見 し治療するべきである。しかし原因が発見できないかまたは完全に治療されない場合が多い。これらの例の多くは多様な抗炎症治療に反応するが,グルココルチコイドが最も効果的な選択肢である場合が多い。
グルココルチコイドは,解 熱,食 欲増進,多幸感などを導くので,炎 症の臨床徴候を改善する。よって,グ ルココルチコイ ドを投与 している症例において手遅れになるまで感染の増悪に気付かないこともある。
どんな決まりにも例外があるように,グルココルチコイド療法は抗生物質投与と併用することによって, Pseudomonas属による耳炎や猫の伝染性腹膜炎といった感染性疾患の免疫産物や炎症を抑制するためにも使用される2″22〕。
グルココルチコイドによる抗炎症療法は,効 果発現速度の要望や治療期間などの多 くの因子により選択される。
呼吸器の炎症により呼吸困難を呈 している症例には急速な薬効の発現が望まれる。
急速に作用を発現 させたい場合は,注 射可能なリン酸製剤またはコハク酸製剤が使いやすい。一般的にはグルココルチコイドの経口投与で十分である。
だいたい,抗 炎症治療は数日間,数 週間,数カ月間を要する。中間型グルココルチコイド製剤は投与量を減らしても効果があるので,最 低量で長期間使用される。
経口薬のプレドニゾンまたはプレドニゾロンは最も頻繁に使われる抗炎症薬(初 回量は犬では0.5~1mg/kg/日,猫では1~2mg/kg/日)であり,1日1回投与または1日2回 分割投与される。生物学的半減期は24~36時間なので分割投与の方がやや効果的である。
いったん炎症が治まったら用量を必要最低限に下げる長期の治療が必要な動物において,長 時間型製剤(例:酢 酸メチルプレドニゾロン)を使用すると,中間型グルココルチコイドと比較して,視 床下部一下垂体ー副腎系を強く抑制し,正 確な用量の使用ができず,明らかな副作用の発現が認められる。
さらに,一 定期間,正 確な診断試験(例:皮 膚アレルギー検査,内 分泌検査)に 悪影響を及ぼす23)。筆者らの意見では,ここ のような製剤でが必要である。確定診断を行い根底にある炎症の原因を除去する。グルココルチコイド療法を始める前に感染性の原因,特 に真菌感染などを除去することは重要である。
なぜならば炎症は本来の生態防御システムに関連しており,グ ルココルチコイドには免疫抑制効果があるので感染に対しての使用は禁忌である。グルココルチコイドは感染に続発 した炎症のある症例において一時的には症状を軽快させるが,感 染を制御できなければ疾患を増悪させたり死亡させたりする場合もある。
グルココルチコイドは,解 熱,食 欲増進,多 幸感などを導くので,炎 症の臨床徴候を改善する。よって,グ ルココルチコイドを投与 している症例において手遅れになるまで感染の増悪に気付かないこともある。どんな決まりにも例外があるように,グ ルココルチコイド療法は抗生物質投与と併用する ことによって, Pseudomonas属による耳炎や猫の伝染性腹膜炎といった感染性疾患の免疫産物や炎症を抑制するためにも使用される。
グルココルチコイドによる抗炎症療法は,効果発現速度の要望や治療期間などの多くの因子により選択される。
呼吸器の炎症により呼吸困難を呈 している症例には急速な薬効の発現が望まれる。急速に作用を発現 させたい場合は,注射可能なリン酸製剤またはコハク酸製剤が使いやすい。一般的にはグルココルチコイドの経口投与で十分である。だいたい,抗 炎症治療は数日間,数 週間,数カ月間を要する。中間型グルココルチコイド製剤は投あるデポ ・メドロールを投与できる疾患は制限される。
筆者らはデポ ・メドロールを,飼 い主が経口投与をしたくない,ま たはできない場合のアレルギーや炎症性皮膚疾患の健康な猫に対 して投与する。デポ ・メドロール治療は特別に猫の好酸球性肉芽腫疾患に対して行われる(4mg/kg,酢酸メチルプレドニゾロンを2~3週 間おきに皮下投与)。 いったん寛解しても治療は必要に応 じて2~3カ 月ごとに続ける必要がある。
免疫抑制療法
免疫介在性溶血性貧血,特発性血小板減少性紫斑病,免 疫介在性関節症,全 身性エリテマ トーデスのような疾患の治療においてグルココルチコイドの重要性を示す多 くの報告がある25)。さ らに,グ ルココルチコイドは猫伝染性腹膜炎や移植組織に対する拒絶反応に伴う免疫学的反応を抑制す
るために使われる抗炎症療法 と同じく,中 間型製剤の経口投与は最も一般的な治療の選択肢である。
免疫抑制作用を起こす投与量は抗炎症作用を起こす投与量よりも多い。一般的に犬には2~4mg/kg/日のプレドニゾンまたはプレドニゾロ ンの初 回経口投与量が推奨 され,猫 には4~8mg/kg/日の投与量が推奨される。
投与量が多いので1日量を2回 に分けて分割投与すると副作用が軽滅でき与量を減らしても効果があるので,最 低量で長期間使用る。免疫抑制療法をプレドニゾンよりデキサメタゾンで開始することを推奨する獣医師もいる。しかし,投 与量が同じ場合どちらの薬が効果的かという報告はない。
筆者らは経口投与が困難なときデキサメタゾン注射を選ぶ傾向にある。そしてできるだけ早くプレドニゾンまたはプレドニゾロンの経口投与に変える。
たとえどのグルココルチコイド製剤を選択したとしても,症 例の治療に対する反応によって初回投与量を減量していく。理想的には,い ったん疾患をコントロールできたらグルココルチコイドは中止するまで徐々に減らしていく。
場合によっては,高 用量のグルココルチコイ ドでしか疾患をコントロールできないこともある。このような状況では,他 の免疫抑制剤(例:ア ザチオプリン)をグルココルチコイ ドの用量を減 らすために併用することができる25)。
グルココルチコイド治療の副作用が受け入れられない動物において,こ の併用治療法は特に効果的である
抗腫瘍療法
全身性グルココルチコイド療法はいろいろな腫瘍に対しても行われる。一般的に,グ ルココルチコイドは犬猫のリンパ腫に対して他の化学療法薬と併用される。
単独で使われてリンパ腫を寛解させる場合 もある(プ レドニゾンまたはプレドニゾロンを2mg/kg/日,PO)。
しかし,グ ルココルチコイド誘発性の多剤抵抗性の発現は寛解期間を短 くし,よ り積極的な化学療法プロトコールによる治療の成功率を減 らす。グルココルチコイドは腫瘍性リンパ球の急速な消滅を導くので,診 断前の投与によりリンパ腫の細胞学的または組織病理学的確定診断が妨げられる可能性がある。
グルココルチコイドは他の腫瘍の治療や腫瘍随伴性状態の治療においても全身投与される。グルココルチコイド療法(多 剤併用法のひとつの成分として)に 反応する腫瘍には,多 発性骨髄腫,あ る種の白血病,肥 満細胞腫などがある。全身性 グルココルチコイドはインスリンの作用を拮抗するので,イ ンスリノーマ症例においては血糖値を上昇させるために使われる(プ レドニゾンまたはプレドニゾロンを0.5mg/kg/日,PO)。
リンパ腫または他の腫瘍状態における高カルシウム血症も全身性グた はプ レドニゾロンを1~2,2mg/kg/1日2回,PO,SC,IV)34〕。腫瘍 に随伴する浮腫 と炎症に対 しては,短期 間のグルココルチ コイ ド療法(例:腫 瘍除去の周術期または治療時),長 期間のグルココルチコイ ド療法(例:脳腫瘍の待機療法)が 行われる。
局所のグルココルチコイド療法
局所の組織が治療の標的である場合は,標 的組織にだけグルココルチコイドを適用するのが理想的である。
局所的に投与されたグルココルチコイドの全身への吸収は完全にはなくせないが,局 所への投与は全身的な副作用を最低限にする3`’36)。 グルココルチコイ ドには局所療法のために考慮されたさまざまな製剤がある。さらに注射可能な製剤によっては局所的な効果が得られる(例:関節痛を軽減する関節内注射)。
これらの製品の意図する効果は局所的なので,製 剤は活性化されたグルココルチコイドでなければならない。すなわちプレドニゾロンは適しており,プレドニゾンは不適切である。
目の治療目とその周辺組織は,時 々全身療法も行われる(例:視神経炎,眼 窩の炎症)が,一 般的には,局 所的なグルココルチコイ ド投与により治療される。
眼科疾患に対してグルココルチコイ ドを使うための基準は,
1)目 の炎症の悪影響を軽減する,
2)水 晶体誘発性ブドウ膜炎のような免疫介在性疾患の治療
の2つ である。
局所のグルココルチコイド療法とは局所または結膜下への投与である。
局所にグルココルチコイドを投与する場合は,目の構造外の炎症性疾患,非炎症性結膜炎,ブドウ膜炎のような前眼部の疾患である。懸濁剤(例,1%酢 酸プレドニゾロン)と水溶液(例:0.1%リン酸デキサメタゾンナ トリウム)は ともに効果があるが,懸濁剤の方がより角膜上皮を透過する。1日 に3~4回 の点眼から1時 間ごとの点眼までその投与回数には差がある。
一般的に,治 療効果を観察 しながら,薬剤の強さよりも点眼の頻度を変えて調節する。眼軟膏(例:0.05%リン酸デキサメタゾンナ トリウム)は 接着時間が長いという利点がある。
長時間型製剤(例:1%酢 酸プレドニゾロン)の結膜下住射は,虹 彩の炎症またはひどい前眼部の炎症の場合に行われる。通常,注 射の後は長時間型グルココルチコイドの最高効果が得られた後,ま たは注射の直後から,局所用のグルココルチコイドを飼い主に点眼してもらう37>。
グルココルチコイ ドは潰瘍を悪化させるので,虹 彩の潰瘍の場合は使用するべきではなく,感 染がある場合は間質の溶解を起こす37)。目に対するグルココルチコイド投与はウイルス感染症では禁忌である。このことから,猫の結膜炎はウイルス性疾患なのでグルココルチコイ ドの使用は禁忌である。結膜下注射の合併症はまれであるが,時 折,注 射部位に肉芽腫ができ外科切除が必要となる場合がある。長期のグルココルチコイ ド使用による目に対する副作用は,ヒ トと比較すると犬猫においては一般的ではない。グルココルチコイドの局所療法においても,全身性に吸収され副作用も発現する
皮膚の治療
グルココルチコイドは皮膚疾患の治療のために全身投与されることが最も多いが,局 所投与では作用の強いものを使 うことがで き,場 合 によっては全身性に投与で きる。 この場合も疾患をコン トロールで きる最低量のグルココルチコイドを投与する。全身性の治療に局所の治療を加えることにより全 身への投与量 を減 らすこ とができる。1%ま たはそれ以下の濃度のハイ ドロコルチゾ ン製剤 は,シ ャンプー,コ ンデ ィシ ョナー,ロ ーシ ョン,クリーム,軟 膏,そ して点眼薬 として入手できる。 これ らの製剤 は抗 ヒスタミン薬のような他の薬物 と併用 してアトピー に伴う痒感 を軽減するときに特 に効果的である。
よ り効果的なグルココルチ コイ ド製剤である,ト リアムシ ノロ ンアセ トニ ド(例:Panalog‐FortDodge,他),ベ タ メ タゾ ン:GentosinTopicalSpray,
Otomax-Schering-Plough,他),フセ トニ ド(Synotic-FortDodge)なル オシノロンアどは紅斑,腫 脹,痒 感 を減 らすの に効果的 だが連 日投与す るべ きではない
これらの製剤を頻繁に使うと,皮 膚の菲薄化,面 ぼう,二次的な感染などの全身的または局所的な副作用が発現する。吸収 による全身への影響は皮膚バリアがない炎症部位における投与で特に問題となる。それはアレ所性グルココルチコイド製品は多数販売されている。これらの短期間の使用は,浮 腫,耳 道腺の過形成,耳 垢,感 染に対する好中球の移動を軽減するのに効果的である。
耳への長期のグルココルチコイド投与は,1%ハ イドロコルチゾン製品に限り少ない回数で行うことができる。
呼吸器の治療
グルココルチコイドは反応性気道疾患に伴う炎症などを軽減するのに適 している。呼吸器への局所投与は鼻腔スプレーと吸入によるが,ヒ トにおいては局所投与の併用はグルココルチコイドの長期間の全身投与による副作用を減らすと報告されている。
最近,定 量噴霧式吸入器を喘息の猫に適用した治療の逸話的な成功が報告されている。
定量噴霧式吸入器は動物用薬:Aer0KatFelineAer0solChamber一TrudellMedicalInternational;800-465-3296)またはヒト用薬を応用することにより使用される。定量噴霧式吸入器はどの薬店でも入手できるスペイサー吸入補助器(例:OptiChamber-Resporonics)にi接続でき,ス ペイサー吸入補助器の反対側には猫用の麻酔マスクに接続できる(図①)。 定量噴霧式吸入器を2~5回 稼動し,猫の顔にすばやくマスクをかぶせる。猫にマスクをした状態で少なくとも10回 は呼吸させる。吸入の深さと回数は薬物の吸入量に明らかに影響する。筆者 らは110~220μg(徴 候の重篤度による)プ ロピオン酸フルチカゾン(Flovent‐GlaxoSmithKline)の定量噴霧式吸入を1日に2回 行うことを推奨している。
局所的なグルココルチコイ ド適用であるこの方法は治療効果が最高に達するまでに10~14日 を要するので,初 回治療においてはグルココルチコイドを全身性に投与するべ きである(プ レドニゾンまたはプレドニゾロン1~2mg/kg/日,PO)。
筆者ら重度から中程度の徴候を示す猫には全身性にグルココルチコイ ドを投与し,徴 候の安定 した猫においては定量噴霧式吸入器を,疾 患のコントロールまたは全身性グルココルチコイド投与の補助 として使うべきであると考えている。
アレルギー性または特発性の鼻炎を示す犬猫に対しては鼻腔内グルココルチコイドが効果的である。
この場合,確定診断(鼻 の画像診断とバイオプシー)に よって腫瘍と感染性疾患が否定されるまでは投与するべ きではない。グルココルチコイド鼻腔スプレーも使用できるが,著 者
らは眼科用の1%酢 酸プレドニゾロン2滴 を両鼻腔に1日2~3回 滴下している。この初期の頻回投与は状態に合わせて回数を減らしていく
胃腸の治療
胃腸管の非感染性炎症はグルココルチコイ ドで治療可能である。胃腸管に対する局所療法は局所の投与が可能な部位に限られる。特に口腔,結 腸,直 腸に対 して行われる。獣医学領域において,好 酸球性肉芽腫の病変内注射は行われるが経ログルココルチコイドの局所療法はあまり行われない23)。ヒトで使用されるグルココルチコイド製剤には,座 薬,注 腸剤,ま たは直腸の泡沫剤がある。高価 ではあるが,筆 者らは犬の難治性大腸炎に対し10%酢 酸ヒドロコルチゾン直腸泡沫剤(CortiformSchwarzPharma)の使用と積極的な全身療法によって治療に成功している。この製品は蓋付きの容器に挿入チューブとともに入っており,こ のチューブを用いて中~大型犬の直腸内に簡単に薬剤を挿入できる。寝る直前に1本 分を挿入する。挿入後に犬が排便 しなければより長く薬剤を保持できる。
関節内の治療法
いくつかの整形外科疾患は,全 身性または局所性のグルココルチコイドによって治療する。全身性のグルココルチコイ ド療法は,免 疫抑制量で免疫介在性関節症に対して行われ,さ らに低用量で他の治療に反応 しない四肢に症状のある変形性関節症の待機的な治療として行われる。グルココルチコイドの局所注射は治療として考えられることはないが,関 節痛に対して待機的に行われる。
グルココルチコイドの関節内注射はヒトとウマの治療においてよく行われているが,小 動物においてはあまり行われない43’44)。 この ような住射は炎症を急速に抑え疼痛を緩和し機能を回復させるが,骨 軟骨欠損症の悪化,
軟骨障害,変 形性骨関節症の悪化,関 節性敗血症などの合併症44)を 引き起こす可能性もある44’45)。小動物の整形外科領域の最も効果的な局所のグルココルチコイ ド療法は,犬 における治療抵抗性の二頭筋の腱鞘炎であろう。
典型的に,犬 では1mg/kgの酢酸メチルプレドニゾロ続するが,治 療中は運動制限しその後徐々に運動させる。
副作用どんな薬物でも多 くの臓器に対する影響が考えられるが,グ ルココルチコイドの副作用もそのように予想すべきである。副作用は非常に軽度なものから命にかかわるものまである(表 ②)。投与量と投与期間が副作用による状態の悪化に直接関与する。投与量の増加や治療期間の延長に伴い副作用もひどくなる。多尿,多 飲,多 食が最も一般的なグルココルチコイドの副作用であり,こ れらが発現する可能性が高いことを獣医師は飼い主に警告しておかなければならない。
医原性副腎皮質機能亢進症は,長 期化したコルチコステロイ ド治療中の犬において認められる。組織学的に,身体的に,そ して検査室検査による医原性副腎皮質機能亢進症の結果からは下垂体性一副腎皮質機能亢進症または副腎性一副腎皮質機能亢進症との鑑別はできない47)。
しかし,下 垂体性一副腎皮質機能亢進症または副腎性一副腎皮質機能亢進症とは異なり,医 原性副腎皮質機能亢進症はコルチコステロイド投与の既往歴があ り,外 因性ACTHに対する反応が抑制されることにより診断できにる。
また,副 作用はグルココルチコイド療法の不適当な停止に関連して起こる。特に長期間(2週 間以上)の 外因性グルココルチコイ ドを急速に停止すると,沈 うつ,食 欲低下,そ して嘔吐などの徴候(コ ルチコステロイ ド離脱症候群)が 現れることがある48)。
。重篤な場合において治療を急速に停止すると,視 床下部一下垂体一副腎系の抑制から副腎に抑制がかかり必要量のグルココルチコイド生産を障害し,命 にかかわる副腎不全状態を引き起こす47)。
グルココルチコイ ドはまた検査結果の誤診の原因にもなる。例えば,グ ルココルチコイドはアルカリフォスフアターゼのような,コ ルチコステロイ ドに特異性のある酵素の活性を増加させる。この結果,胆 汁うっ滞性肝炎があるかのようにみえる。グルココルチコイドを投与されている症例において高血糖値が測定されたならば糖尿病も疑われる。そしてグルココルチコイ ドを投与されている症例では総T4と 遊離T4が 増加 しており,よ って甲状腺刺激ホルモンに対する応答が鈍く49),甲 状腺機能低下症という誤った診断を招 く。最終的に,た とえ局所療法であってもグルココルチコイド療法は視床下部.下 垂体 一副腎系の機能検査に影響する50ヤ52)。外因性グルココルチコイドによる視床下部一下垂体 一副腎系抑制の持
続は,薬 の効果,製 剤の型,そ して投与期間による。それぞれの製剤に関してのガイドラインはないが,1mg/kg/日で5週 間プレ ドニゾンを投与されていた犬は,グ ルココルチコイド療法を停止して2週 間後に視床下部一下垂体一副腎系の機能が回復したと報告されている52)ココルチコイ ドの代謝と排泄を変化させるので,投 与したグルココルチコイ ドの用量によって生物学的影響が増減する。さらに,グ ルココルチコイドは同時に投与 した薬物の効果や毒性に影響を及ぼす54)。
減薬プロトコル
麻酔薬と同様にグルココルチコイ ドは任意の用量によってではなく効果を考慮して使用するべ きである。しかし,麻 酔薬とは異なりグルココルチコイ ドの効果は急速には発現しないので,治 療にはしばしば数週間から数カ月を要する。最低用量のグルココルチコイ ドを投与し効果を得ることを目標にすべ きである。
疾患がコントロールされていることが臨床症状から予測 されたら(例:特 発性血小板減少性紫斑病において血小板数が正常化する,炎 症性腸疾患において下痢が止まるなど)グ ルココルチコイドの用量を減 らしていくべきである。減量に関して理想的なプロトコールはないが,基本的な原則はある。まず第一に,臨 床徴候を住意深 く観察すべきである。
用量を減 らした後,すぐに臨床徴候が悪化 した場合は用量の減少が急速すぎたためである。
第二に,減 量する量は疾患の重篤度による。命にかかわる疾患(例:免 疫介在性溶血性貧血,特発性血小板減少性紫斑病)症 例に投与しているグルココルチコイドを減量する場合は,他 の疾患に使っているグルココルチコイドよりゆっくりと減量する。第三に,投 与間隔を延長させながら減量すると,生 物学的な薬効を維持する一方,視床下部①下垂体一副腎系の抑制を回復させる。例えば,1日2回,5mgのプレドニゾンを投与していた場合,単純に1日2回 の1回 分の量を減らすより,ま ず1日1回,10mgに変更する方がよいであろう。その後,1日1回 の量を逐時的に減量していく。1日1回 量が抗炎症作用の最低量(犬 で約0.5mg/kg)に なってから,減 量間隔を1日 おきに変える。1日 おきに投与する用量は今までの2倍,そ のまま,ま たはその間の量にする。2日 に1回 の投与で動物が安定したならば,疾 患の再発に注意しながら用量を逐時的に減量する。理論的には,1日 おき(ま たは2日 おき)の投与量でも,動 物に薬を投与しない日で視床下部ー下垂体 ①副腎系を抑制状態から回復させることがで きるo'5)。この1日 おきの減量計画はグルココルチコイ ド製剤の生物学的持続時間に基いている。そしてこの減量計画は中間型グルココルチコイドに対 して適応される。例えば,デ キサメタゾンはこのような減薬計画は有効ではない
動物医療におけるコルチコステロイド シンボジウムchatGPT要約
🔹【1. ステロイドの重要性と使用状況】
- 多くの動物病院ではICUや救急対応体制が整っていないが、それでもステロイドは幅広く用いられている。
- ステロイドは皮膚病、アレルギー、眼、消化器、呼吸器、整形外科、神経、腫瘍など、ほぼすべての診療科で重要な治療薬。
- 感染症の一部にも使用される。
🔹【2. 投与法と副反応】
- 多彩な剤形(点眼、軟膏、噴霧剤、錠剤、注射)があり、目的に応じた使い分けが可能。
- 副作用として、多飲多尿、過食、糖尿病、皮膚の石灰化、医原性クッシング症候群などが報告されている。
- 飼い主の不安や誤解を防ぐため、十分な説明が不可欠。
🔹【3. 基礎的知識:生理学と猫の特徴】
- コルチコステロイドは副腎皮質ホルモンで、内因性ホルモン(特にコルチゾール)と関係がある。
- 猫は犬よりもステロイドに反応しにくく、プレドニゾロンを高用量で投与する必要がある。
🔹【4. 臨床的適応と禁忌】
◎ 主な適応症:
- 皮膚疾患(アトピー、ノミ過敏症、自己免疫疾患)
- 眼疾患(ただし、角膜潰瘍には禁忌)
- 免疫性血液疾患(溶血性貧血、血小板減少症)
- 消化器疾患(IBD、リンパ管拡張、好酸球性腸炎)
- 呼吸器疾患(喘息、慢性気管支炎)
- 神経・整形疾患(椎間板ヘルニア、関節炎)
- 腫瘍(特に肥満細胞腫に対し、補助療法として)
✖ 禁忌:
- 真菌感染、膿皮症、毛包虫症、角膜潰瘍、特定の肝疾患など。
🔹【5. 投与の工夫と注意点】
- 最小有効量で治療を開始し、可能であれば1日おきの投与で副腎のフィードバック抑制を軽減。
- 長期使用は慎重に。局所使用でも全身作用が出ることがあり、飼い主やスタッフの曝露対策も必要。
- **「症状を抑えるが、病気そのものを治すわけではない」**という基本を忘れてはならない。
🔹【6. 結論】
- ステロイドは非常に効果的な治療薬だが、副作用やリスクも多いため、正しい知識と慎重な使用が求められる。
- 飼い主との信頼関係や説明責任を果たし、誤解によるトラブルを防ぐことも重要。
- 「コルチコステロイドを使えば剖検室まで歩かせることができる」という古い格言にあるように、強力な効果の裏にあるリスクを常に意識すべきである。
全ての動物病院に集中治療室があるわけではないし、救急医療が業務の中心になるような動物病 院はそれほど多くない。それでも獣医は医療の現場でステロイドを頻繁に使用する。様々な疾患 の治療に欠かすことのできないステロイドについて、本稿ではその合理的な使用法について考察 する。 ステロイドは皮層疾患をはじめアレルギー性疾患、眼疾患、胃腸疾患、心肺疾患、整形疾患、歯 科疾患に及ぶ動物医療のあらゆる分野で使用されている。意外なことに、いくつかの特定の感染 性疾患もコルチコステロイドの適応となる。 ステロイドは広範な薬理作用を持つことから、使用方法を細かくデザインすることができる。小 さな金槌で済む仕事に巨大な梶棒を使う必要はない。 ステロイド剤は点眼剤、軟膏、噴霧剤、錠剤、注射剤(溶液・懸濁液)など、様々な剤形で入手 でき、剤形が多彩であるため、副反応を最小限に抑えながら理想的な投与方法を選択することが できる。確かに副反応はいつも無害で可逆的であるとは限らないし、多尿多飲、過食症、治癒の 遅延、医原性クッシングなどの問題を耳にすることも多い。 しかし、飼主によっては「ステロイド」と聞いたとたんに拒絶的になり、愛するペットにそんな ものを与えるなんてとんでもないという態度をとることがある。訴訟が身近になった現在、裁判 沙汰になるような誤解を招かぬよう事前に十分な説明を尽くすことが大切である。獣医師自身を 守るというだけでなく、ステロイドの様々な利点をきちんと飼い主に理解してもらう努力が必要 である。 コルチコステロイドの基本: 内因性のステロイドは副腎皮質から産生されるホルモンである。視床下部で作られる副腎皮質刺 激ホルモン放出因子(CRF)により脳下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌され、 ACTHにより副腎皮質において副腎皮質ホルモン(グルココルチコイド)が産生される(束状帯 および網状帯)。アルドステロン等のミネラルコルチコイドは主に副腎の球状帯で産生され、主 に電解質代謝(Na、Cl,K)に関わる。 主な内因性ステロイドはコルチゾールである。ヒトでは1日におよそ10mg産生されるが、重度 のストレスなど特殊な条件下ではこの10倍に達することがある。犬では1日当たり0.1~2 mg/kg産生される。猫における産生量は不明である。 獣医はこれまで長い間、猫のコルチコステロイドに対する抵抗性に悩まされてきた。この問題に 関する研究は少ないが、いくつかの説がある。猫は皮膚と肝臓においてグルココルチコイドの受 容体が少なく、また受容体が速やかに回復するようである。したがって臨床では、猫にはプレド ニゾンではなくプレドニゾロンを、通常犬の2倍の用量で投与するのが望ましい。また猫はグル ココルチコイドに関して日内変動が 猫では成熟好中 球増加、リンパ球減少、好酸球減少などの白血球のストレスパターンを認めることが多い。ステ ロイド性肝障害がまれな猫においても、インスリン抵抗性で糖尿病のリスクが高い場合などは慎 重を期さねばならない。(Loweetal,2009;Graham-Mizeetal,2008) 臨床で用いられるグルココルチコイドは合成物であり、肝臓で代謝されてから生物学的活性を得 るものもある。作用の強度と持続時間は投与経路だけでなく、分子構造、水溶’性によって異なる。 理想的には、最小有効用量から始め、可能であれば1日おきに経口投与する。これは視床下部・ 下垂体・副腎皮質軸に正常なフィードバックをさせるためである。 酢酸メチルプレドニゾロンは水溶性に乏しいため、副腎抑制作用が延長する。
コルチコステロイドには数多くの作用があるが、第一の作用は恒常性の維持であり、いずれの作 用もすべての代謝過程に影響を及ぼす。 ・炭水化物、脂肪、タンパク質の代謝 ・線維芽細胞の増殖(創傷治癒) ・炎症反応 ・水分および電解質平衡 ・赤血球新生 ・中枢神経系機能 ・胃酸分泌 ・免疫系(先天的) ・筋力・筋機能 コルチコステロイドは液性および細胞性免疫反応、炎症性メデイエータ(インターロイキン等) の産生、炎症性細胞の遊走、マクロファージまたは樹状細胞の負食作用を抑制する。 副反応:種類、程度ともに様々である。 ステロイドの最も一般的な副反応として、治癒の遅延、多飲他尿、多食、体重増加、肥満、糖尿 病、医原性副腎皮質機能冗進症、皮膚の石灰沈着症など、獣医や一部の飼主にもよく知られてい るものから、猫のうっ血性心不全(Smithetal,2004)や犬の肺石灰化症(B1oisetal, 2009)なども稀に発生する。 ステロイドによる副反応は猫よりも犬で顕著に認められるが、猫はステロイド投与に対して有害 反応を示さないということではない。 一般的な短期および長期的副反応には次のようなものがある。
皮膚疾患 長期的副反応 医原性副腎皮質機能冗進症(クッシング病): 体重増加 「太鼓腹」(体脂肪の再分配および筋委縮) 脱毛症:限局性非癌津性(Fujisawa,2009) 面飽 皮膚石灰沈着症(減)肺石灰化症(獄) (Bloisetal,2009) 膿皮症 毛包虫症 尿路感染 糖尿病 騨炎 消化管漬傷 皮膚脆弱症(‘) 鯵血性心不全(通)(Smithetal,2004) 皮膚疾患はステロイドが最も一般的に使用される分野である。グルココルチコイドは掻捧に対 して魔法のような効果を発揮するが、適切な診断が得られなければ、疾患は(復讐するかのよう に)再発する。愛犬に注射を打てば魔法のようにかゆみが治まることを飼主は熟知しているため、 このような「かゆみ止め」を打つのを断るには多大な外交術を要することがある。
局所軟膏や噴霧剤は限局性病変に使用することができるが、それでもやはり限局性非掻捧性脱毛 症等の副反応を引き起こす。(Fujisawa,2009) 最近発売されたアセポン酸上ドロコルチゾン噴霧剤(CortavancenI)は2週間使用しても大きな 副作用はみられなかった(Nuttalletal,2009) ステロイドを局所的に用いる場合、飼主に手袋を着用するなどして自分の体を守るように警告す ることが極めて重要である。同様に、飼主が塗り薬を使用する場合にもペットを保護する必要が ある。飼主が塗り薬を使用した後に医原性副腎皮質機能冗進症を発現したことが報告されている。 (Ridgway,2003) 犬のアトピー性皮膚炎やノミ過敏症等のアレルギー性疾患はグルココルチコイドの主な適応症で あるが、食物有害反応に対するステロイド療法は期待はずれであることが多い。複数のアレルギ ーがある犬では、累積した津みを抑えて掻岸の闘値を超えないように維持するためにステロイド の使用が有用である。 グルココルチコイドの適応症としては、上記の他に華麻疹および血管性浮腫、犬の若年性蜂嵩織 炎(若年性膿皮症)、特発性無菌性脂肪織炎、自己免疫疾患(落葉状天庖痛…)、猫好酸球性症 候群、耳炎などがある。毛包虫症、膿皮症および真菌感染症に対する使用は禁忌である。 眼疾患 コルチコステロイドは眼の炎症に対しても抑制作用があるが、通常結膜に適用し、全身投与は稀 である。コルチコステロイドは局所の免疫反応を抑制し、プロテアーゼおよびコラゲナーゼの活 性を強めて角膜の治癒を抑制するため、角膜潰揚に対しては絶対に禁忌である。 猫へルペスウイルス等のウイルス性疾患の治療に使用する場合は注意が必要である。20年以上 前になるが、実験的に感染させたSPF猫の研究において、感染前にベタメタゾンを結膜下注射し た猫は慢性間質性角膜炎を呈し、涙液産生減少、石灰化帯角膜症および角膜剥離を発現した。 (Nasisseetal,1989)。 血液学: 主な適応疾患は溶血性貧血や血小板減少症等の免疫介在性血液疾患である。研究者によっては、 ヘモバルトネラ症の管理に使用する際は厳格なノミ防除と抗生物質治療を併用することを推奨し ている。 消化器疾患および肝疾患: 一連の診断検査後に、炎症や免疫を抑える必要がある場合はいつでもグルココルチコイドが有用 である。例えば劇症騨炎やEPI(「古典的」治療の失敗)、リンパ管拡張、リンパ球性プラズ マ細胞性腸炎、好酸球性腸炎、炎症性腸疾患(慢‘性大腸炎)、虹門フルンケル症(シクロスポリ ンAおよび低アレルギー食と併用)。 肝疾患の徴候は非特異的で、コルチコステロイド(剤形にかかわらず)を含め肝酵素が上昇する 原因は多様である。犬ではステロイド性肝障害が頻繁に報告されている(猫では非常に稀であ る)。この疾患は肝細胞におけるグリコーゲンの蓄積による肥大化現象(バルーニング)および 肝腫大によって引き起こされ、血液検査ではアルカリホスファターゼの上昇が認められる。症状 は副腎皮質機能冗進症にしばしば類似するが、投薬を中止すれば通常12週間以内に回復する。 しかしながら、ステロイドは慢性炎症性肝疾患の適応となる。確定診断が得られてない場合や猫 のリンパ球性胆管炎において長期間有益な効果が見られない場合は、ステロイドの使用は避けた 方が良い(Rothuizen,2008
呼吸器疾患: 犬と猫のいずれにおいても、瑞息や慢性気管支炎等のアレルギー性呼吸器疾患は全般的にステロ イドの適応となる。
ステロイドは肺気腫および特発性肺線維症やある種の気管支肺炎で症状を軽減する。 jngioszmn”Iusvasor”のような寄生虫感染の場合は、グルココルチコイドは塞栓性肺炎やア ナフィラキシーの予防に有用である。 腎泌尿器疾患: 尿検査ではグルココルチコイドなどの影響を考慮する必要がある。ステロイドは尿比重を低下さ せ、尿沈澄を希釈する。 腎疾患がグルココルチコイドの適応となることは稀であり、一般的にその使用は勧められない。 基礎疾患がステロイド反応性であると分かっている場合は、通常通り慎重に投与する。全身性エ リテマドーデスの動物では糸球体腎炎がステロイド投与の指標となる(Grauer,2007) 骨関節疾患および神経疾患: 変形性関節症(骨関節炎)の最良の治療法はやはり根本原因の治療であり、例として肥満動物の 体重を減らすこと等である。短期の治療としてグルココルチコイドが選択されることがある。ス テロイドの関節内注射は痛みを緩和するが、ステロイド性関節障害のリスクがあることを忘れて はならない。 神経学的症状、キアリ様症候群、脊髄空洞症、椎間板疾患、脊椎・脊髄腫傷は慎重に治療する必 要がある。この点については本シンポジウムにおいて救急医療の専門家が講演で取り上げる予定 である。 腫揚: ステロイド、特にプレドニゾロンの経口投与は犬と猫の癌治療に使用されることが多い。ステロ イドには軽度の鎮痛効果があり、幸福感をもたらして食欲を刺激する場合もある。 化学療法の際にCCNU(ロムスチンⅧ)やビンブラスチン等と共に使用されることが多い。 肥満細胞腫: プレドニゾロンは単独または他の化学療法剤と併用して用いられてきた。全身性または病巣内に 単独で投与する場合、その目的は通常炎症のコントロールであるが、グルココルチコイドは肥満 細胞腫の増殖に影響を及ぼすことがinvitro試験で示されている。生存率に対する臨床的有効 性は一定しない。 犬肥満細胞腫のためのビンブラスチン、プレドニゾロン、CCNU(ロムスチン)のプロトコル ビンブラスチン:2mg/m21V週1回で4週間、その後隔週投与 プレドニゾロン:1mg/kgPOBID1-2週間、その後SIDに減薬、その後隔日に漸減 CCNU: 70mg/m2PO21日毎または90mg/m2PO28日毎
結論: 適切に使用すれば、コルチコステロイドは優れた薬剤である。致命的な副反応の可能性を排除す るためには、代謝特性や起こりうる副反応に関する深い知識が必要である。クライアントとのコ ミュニケーションにも注意を払わなければならない。経口薬や塗り薬は優れた治療の選択肢であ るが、飼主や臨床スタッフの保護を第一に考えなければならない。 グルココルチコイドが治療するのは症状だけであり、疾患そのものではない。「コルチコステロ イドを投与すれば剖検室まで歩かせることができる」という言葉を忘れてはならない。(Albert Dewaele,1981)
この文書は、コルチコステロイドの救急医療での使用についての詳細な説明を提供しています。要約すると以下のようになります:
1. コルチコステロイドの種類
- ミネラルコルチコイド(MC): 主にアルドステロンが含まれ、ナトリウムの再吸収とカリウムの排出を助け、血液量を回復させます。アジソン病やアジソンクライシスの治療に使われます。
- グルココルチコイド(GC): ヒドロコルチゾンやプレドニゾン、デキサメサゾンなどがあり、炎症や免疫反応の調整に利用されます。特にGCは、急性の免疫介在性疾患や炎症性疾患において重要な治療薬です。
2. 各種グルココルチコイドの特徴
- ヒドロコルチゾン: 効果が早く、持続時間が短い。アジソンクライシスや手術中に使われます。
- プレドニゾン・プレドニゾロン: 抗炎症効果が高く、持続時間も中程度。注射・経口の両方で使用されます。
- デキサメサゾン: 非常に強力な抗炎症作用を持ち、持続時間も長い。特に炎症がひどい場合に使用されます。
3. グルココルチコイドの作用
- 心血管系: 血圧の上昇、血管収縮作用。
- 免疫系: 炎症反応を抑制し、感染に対する感受性を高めます。特にT細胞や好中球の活性を抑制します。
- 代謝系: 糖新生を促進し、エネルギー供給に関わる作用があります。
- 腎臓: ナトリウム再吸収を助け、水分バランスを調整します。
4. 救急医療におけるグルココルチコイドの適応
- 免疫介在性疾患: 免疫系が関与する疾患(例:免疫介在性溶血性貧血)に使用。
- 心肺脳蘇生法(CPCR): 心肺停止後の蘇生において、特定の状況下での使用が検討されています。
- ショック・重篤な外傷: 使用には議論があり、使用すべきかは症例に依存します。
- 呼吸器系疾患: 上気道の炎症や免疫介在性呼吸器疾患(例:猫の喘息)に使用されることがあります。
5. グルココルチコイド使用時の注意点
- 感染症: GCは免疫抑制作用があり、感染症を悪化させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。感染が疑われる場合、十分な検査と診断を行うべきです。
- 神経疾患: 頭部外傷患者にはステロイドの使用が推奨されていない研究結果もあり、その使用に関しては慎重に判断する必要があります。
結論
コルチコステロイドは、救急医療において非常に有用ですが、使い方には細心の注意が必要です。特に免疫系や感染症への影響、そして薬剤の種類や投与量について、具体的な症例に応じた適切な判断が求められます。
IsabelleGoy-Thollot,DVM,PhD
〃
SIAMU,EcoleNationaleV6t6rinairedeLyo、’1avenueBourgelat69280MarcyL,Etoile,Fraエlce.コルチコステロイドは人と動物の救急救命医療に数十年にわたって使用されている。コルチコステロイドはミネラル(鉱質)コルチコイド(mineralcorticoid,MC)とグルコ(糖質)コルチコイ
ド(glucocorticoid,GC)の2群に大別できる。GCはMCよりも一般的に使用されている。本稿では主にGCについて記述する。MCは腎臓にアルドステロン様作用を及ぼし、遠位ネフロンにおけるナトリウム再吸収およびカリウム分泌を促進する。GCにはヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、デキサメサゾン等があり、炎症および免疫反応の調整作用を有する。
1.2種類のステロイド
1.1.ミネラルコルチコイド(MC)
主要な内因性MCはアルドステロンである。脱水による血液量減少などで腎血流量が低下すると、
アンジオテンシン11(AII)の影響により副腎皮質からアルドステロンが分泌される。アルドステ
ロンは高カリウム血症でも放出され、ACTHの影響下でも少量分泌される。アルドステロンは腎
臓に対し2つの主要な作用、すなわちナトリウムの保持による水の再吸収(有効循環血液量の回
復)とカリウムの排池を促す(25)。
MCが適応となるのは、安定後のアジソン病の管理、アジソンクライシスとして知られるアジソ
ン病重篤患者の救急治療、またはアジソン病が強く疑われるがACTH刺激試験の結果が得られて
いない重症例に限られる。ピバル酸デゾキシコルチコステロン(DOCP;Percorten-VQNovartis,
NorthAmerica)は注射用MC、酢酸デゾキシコルチコステロン(DOCA;Syncortyl③,Sanofi
Aventis,Europe)およびフルドロコルチゾン(FlorinefAcetate⑪,Monarch)は副腎機能低下症の
動物に使用される一般的なMC剤である。DOCPおよびDOCAはGC活性がない。フルドロコルチ
ゾンは経口合成ステロイドで、GC活性および顕著なMC活性を有する(25)。
1.2.グルココルチコイド(GC)
GCは糖代謝に関与することからこの名前がつけられた。主要な内因性GCはコルチゾールであり、
副腎皮質のコレステロールから作られるステロイドホルモンである。コルチゾールは概日リズム
により少量分泌され、病気、外傷、手術等のストレスにより多量に分泌される。GC受容体は体
内のほとんどすべての細胞の細胞質に存在する。したがって、このホルモンには既知そしておそ
らくは未知の多くの生理的作用がある(25)。
2.各種のグルココルチコイド
GCの分子構造の違いにより、GC(抗炎症性)活性が高く、MC活性が低い合成化合物が開発さ
れてきた。これらの化合物の活性上昇は、GC受容体に対する親和性が高いこと、また血紫クリ
アランスが遅いため組織曝露が増加するためである。またこのような分子構造の違いは、生物学
的作用の持続時間に顕著な影響を及ぼす。一般的に、内因性コルチゾールに分子構造がそれほど
変わらないGC(コルチゾン、ヒドロコルチゾン)はMC活性が高く、抗炎症活性の効力が低く、
作用の持続時間が短い(<12時間)。逆に構造変化が著しい薬剤(デキサメサゾン)はMC活性
がなく、抗炎症活性の効力が非常に強く、作用の持続時間が長い(>48時間)。構造変化が中等
度の薬剤(プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン)は中等度の効力特性および
作用の持続時間(12~36時間)を有する(14,25,45)。救急救命医療に最も頻繁に使用される
GCの剤形は注射剤(ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロ
ン、デキサメサゾン)であるが、噴霧剤として用いるものもある(フルチカゾン、ブデソニド)。
12
2.1.ヒドロコルチゾン
ヒドロコルチゾンの構造は内因性コルチゾールと同じであり、そのままで生物学的活性を示す。
ヒドロコルチゾンは作用の発現が早く、作用の持続時間が短い(<12時間)。ヒドロコルチゾン
はMC活性があることから、アジソンクライシスまたは麻酔や手術中の使用において理想的であ
る。注射用上ドロコルチゾンは危篤状態の患者における相対的副腎不全の治療の第一選択薬と
しても用いられる(25).
2.2.プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン
プレドニゾロンおよびプレドニゾンは構造変化が中程度であり、MC活性がほとんどなく、抗炎
症性作用が高く作用時間は中程度である(12~36時間)。メチルプレドニゾロンはプレドニゾロ
ンに非常に似ているが、MC活性がない。これらの薬剤はヒドロコルチゾンの約5倍の抗炎症作用
を有する。プレドニゾロンは投与により生物学的活性を示すが、プレドニゾンが活性化するため
には肝臓でプレドニゾロンに変換される必要がある。プレドニゾンは経口剤しか入手できないが、
プレドニゾロンは経口剤、注射剤、点眼剤および他の剤形で入手可能である。これらの一般的な
製剤はすべて作用の発現が早い(14,25)。
2.3.デキサメサゾン
デキサメサゾンは構造変化が大きく、MC活性がなく、抗炎症活性が非常に強く、作用の持続時
間が長い(>48時間)。デキサメサゾンは肝による代謝を受けずに生物学的活性を示し、プレド
ニゾンの約7~10倍、ヒドロコルチゾンの約30倍の抗炎症作用を有する。最も一般的な製剤(デ
キサメサゾン、デキサメサゾンリン酸ナトリウム)の作用持続時間は数分~数時間である(14,
25)。
2.4.フルチカゾン
フルチカゾンおよび他の同種の薬剤(ブデソニド)は構造が高度に変更されたGCで吸入剤とし
て用いられる。ヒトでは瑞息の治療薬として用いられる。吸入用GCは分子サイズが大きく、局
所に投与されることから、全身投与されるGCよりも全身性の副反応が少ない。吸入用GCは動物
ごとの吸入器(AeroKat③)が必要である。これらのGCは作用発現に1日以上の時間がかかるため、
瑞息重積状態の猫の管理にはふさわしくないかもしれない。この場合は注射用ステロイドの方が
おそらく容易であり、短時間で効果が得られる(14,25,38)。
3.救急救命医療におけるグルココルチコイドの主な作用(45)
GCは哨乳類ではほとんど全ての種類の細胞に効果を示す。
3.1.心血管系
GCは毛細血管透過性を低下させ、血管を収縮させる。GCは比較的軽度の陽性変力作用を示し、
血管収縮作用と血液量増加作用により血圧が上昇する。
3.2.細胞
GCは線維芽細胞の増殖、遊走抑制因子に対するマクロファージの反応、リンパ球の感作および
炎症メデイエータに対する細胞性反応を抑制し、またリソソーム膜を安定化する。
3.3.造血系
GCは循環血小板、好中球および赤血球数を増加させるが、血小板凝集を抑制する。GCは末梢リ
ンパ球、単球および好酸球を減少させる。
3.4.消化管および肝臓系
GCは胃酸、ペプシン、トリプシンの分泌を増加させる。ムチンの構造を変化させ粘膜細胞の増
殖を低下させる。肝臓では肝細胞中の脂肪およびグリコーゲン沈着を促し、血中アラニンアミノ
トランスフェラーゼ(ALT)、ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ(GGT)および血清アル
カリ性リン酸塩濃度を上昇させる。
3.5.免疫系
GCは血中Tリンパ球濃度の低下、リンフォカインの低下、好中球・マクロファージ・単球の遊走
抑制、インターフェロン産生の低下、貧食作用・遊走性の抑制、抗原処理および細胞内殺菌の抑
制に関わる。また補体カスケードを遮断し、感染の臨床徴候を隠ぺいする。要約すると、GCは
サイトカインの産生および好中球・マクロファージ活性を顕著に抑制し、細胞性免疫(T細胞活
性)を阻害するため、感染への感受‘性を上昇させる。
〆?、§、
/嬬砺、
13
3.6.代謝系
GCは炭水化物、脂肪、タンパク質代謝の調整をはじめとする数多くの重要な’恒常性維持機能を
有する。グルコース新生、グリコーゲン蓄積および糖の末梢放出を促す。肝臓のグルコース産生
を上昇させ、筋肉におけるグルコースの取り込みおよび代謝を低下させる。
3.7.腎臓における水分および電解質調節
GCはカリウムおよびカルシウムの排池、ナトリウムおよびクロールの再吸収を促し、細胞外液
量を増加させる。
4.救急救命医療におけるグルココルチコイドの適応
GCは免疫介在性および炎症性疾患の治療、特定の造血器系腫蕩の管理、そして内因性コルチゾ
ール産生が低下した動物のための補充療法に用いることが多い。高カルシウム血症の治療やイン
スリノーマ患者における血中グルコース濃度の管理にも使用される。ショック、全身性外傷、中
枢神経系外傷に対するステロイドの使用については議論が分かれる。
4.1.副腎機能低下症
4.2.心肺脳蘇生法(cardiopulmonaryandcerebralresuscitation,CPCR)
穏砺§
侭憲鞘
獣医教育病院で最近行われた後ろ向き研究では、心肺停止(CPA)後に心肺脳蘇生法(CPCR)
により心拍再開(ROSC)した犬161匹および猫43匹を対象に、その臨床転帰、治療、事象などの
の関連性を検討している(29)。コルチコステロイドを投与せずに心拍再開した犬の割合よりも
コルチコステロイド投与群で心拍再開した犬の割合の方が大きかった。しかしコルチコステロイ
ドを投与した犬は少数であったため、この所見は見せかけの可能性があり、コルチコステロイド
の投与したタイミングに原因があったのかもしれない。心拍再開前に投与したとする努力はなさ
れているが、実際は心拍再開後に投与した例もあったかもしれない。しかし蘇生中のコルチコス
テロイドの効果の大きさを考慮すると、潜在的な有益性は検討するに値すると考えられる。人で
は救急科への搬送時にヒドロコルチゾンが投与された場合、病院外で心肺停止した際の心拍再開
を有意に改善することが示されている(57)。Hohneisterら(2009)は、心肺脳蘇生における短
時間作用型コルチコステロイドの単回投与について、コルチコステロイドは比較的安価であり、
この処置に起因する死亡率が低いことから、心肺停止の患者に選択的に用いることは正当である
と結論づけている(29)。しかしこの見解はPlunkettとMcMickaelinの小動物の心肺蘇生に関する
最新情報とは一致していない(46)。論文中で著者らは心肺蘇生におけるGCの使用を推奨して
いない(46)。
4.3.心原生ショック
心原生ショックは、血管内容量は問題なくとも心機能障害のため細胞代謝が低下した状態をいう
(13)。臨床徴候は全身の低潅流状態によるもので、収縮または拡張障害、不整脈等により心拍
出量が低下すると共に前負荷が上昇し、心原生ショックを引き起こす。収縮障害の最も一般的な
原因は拡張型心筋症である。機械的障害に続発する収縮障害(大動脈弁狭窄症、肥大性閉塞性心
筋症、急性僧帽弁逆流など)は稀である。心タンポナーデ、肥大型心筋症、頻脈性不整脈に伴い
拡張障害が発現することもある。第3度房室ブロックや洞不全症候群等の重度の徐脈性不整脈は
心拍出量の著しい低下から心原生ショックを引き起こすことがある(13)。治療の目的は、心拍
出量の改善により組織潅流および細胞代謝を正常化し、全身に酸素を供給することである。心原
生ショックの救急処置にGCを使用する必要はない。
4.4.呼吸器系疾患と呼吸困難
4.4.1.披裂軟骨浮腫、上部気道閉塞による炎症
抗炎症用量のデキサメサゾン(0.1~0.2mg/kg)およびプレドニゾロン(0.5~2mg/kg)の単回投
与は、披裂軟骨浮腫等の急性疾患や短頭種症候群等の上部気道閉塞に伴う炎症に使用されること
が多い。有用性を示す具体的なエビデンスはないが、禁忌のない患者では低用量の単回投与が有
用となる場合があり、救命効果が期待できる。高用量(>2mg/kgプレドニゾロン)は用いない
(34,52)。
14
4.4.2.無菌性免疫介在性および炎症性呼吸器疾患
GCは猫の瑞息、犬のアレルギー性気管支炎、好酸球性気管支肺疾患など、急性の無菌性免疫介
在性および炎症性呼吸器疾患の治療に重要な役割を担う。このような疾患ではまず最初に免疫抑
制用量のGC(プレドニゾロン2~4mg/kg/day)を投与する。通常数週間から数カ月かけて漸減し、
動物によっては徐々に、完全に投薬中止することができるかもしれない。これらの疾患の殆どに
おいて感染性疾患を検討する必要があり、FNAや気管支肺胞洗浄などの適切な検査を行うべきで
ある。感染症の可能性が除外できない場合は、GCの使用には細心の注意が必要である(10,14,
34,38)。
4.4.3.感染性呼吸器疾患
二次性炎症が臨床症状の大きな要因であると思われる場合の救急処置を除き、一般に感染症の動
物にはGCを使用しない。GCは犬糸状虫症の気道過敏性の治療に推奨され、猫ではこの疾患の治
療の第一選択薬となる。また犬の感染性気管支炎の炎症にもステロイドが使用されている(適切
な抗生物質治療と併用する)(10,14,35)。
4.5.血液学的エマージェンシー
4.5.1.造血器系の免疫介在性疾患
ステロイドは細胞性免疫を抑制するため、犬や猫の免疫介在性溶血性貧血および血小板減少症の
治療に不可欠な薬剤となっている。急性の危機的状態にある患者に対する初期治療として、デキ
サメサゾンまたはデキサメサゾンリン酸ナトリウム0.6~2mg/kg/dayIV(単回または分割投与)、
あるいはプレドニゾンまたはコハク酸プレドニゾロンナトリウム1.1~3.3mg/kglVBIDを用いる。
治療に反応する動物では通常7日以内に改善が認められるが、4週間かかることもある。赤血球
数または血小板数が上昇するまで初期用量を継続し、導入後少なくとも2週間は漸減しないほう
が良いと思われる。ダニ媒介性の犬の免疫介在性赤血球または血小板疾患においてもステロイド
が使用されている(テトラサイクリンなどの適切な抗菌治療と併用)(14,31,44)。
4.5.2.造血器腫蕩一リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、肥満細胞腫
GCは一般に造血器腫傷のための化学療法に併用される。犬と猫ともに通常デキサメサゾンまた
はデキサメタゾンリン酸ナトリウムを0.2~0.25mg/kgで開始する。L‐アスパラギナーゼを併用
する場合は、GCの前投与によりアナフイラキシー様反応発現の可能性を低下させる。これらの
疾患の動物には、化学療法の一環としてプレドニゾンまたはプレドニゾロンを継続的に経口投与
(2mg/kgSID)することが多い。できる限り確定診断後にGC治療を開始ようにする(14,58)。
4.6.その他の無菌性免疫介在性炎症性疾患
救急救命室または集中治療室でよくみられる疾患は、若齢大型犬のステロイド反応性髄膜炎、肉
芽腫性髄膜脳炎、非感染性免疫介在性肝炎または胆管炎、そして免疫介在性皮膚疾患である。こ
れらの疾患の殆どにおいて初期に免疫抑制性用量のGC(プレドニゾロン2~4mg/kg/day)を投与
する。感染症の可能性が除外できない場合は、GCの使用には細心の注意が必要である。
GCの抗炎症用量はある種の感染症が関与する重度の炎症に対して有益であるという意見がある。
一般にGCを感染症の動物に使用するべきではないが、二次性炎症が臨床症状の大きな要因と思
われる救急の場合はその限りではない。中枢神経系の真菌感染に起因する脳浮腫症状の管理にも
ステロイド剤が(適切な抗生物質治療と併用して)使用されてきた(14)。
4.7.神経疾患
4.7.1.頭部外傷
頭部外傷患者においてはステロイドの使用は推奨されていない。獣医療では関連研究はなく、ヒ
トの医療でもごくわずかしか発表されていないが、その中でも最も重要な研究はMRCCRASH
(CoIticosteroidRandomizationafterSevereHeadinjury)である。1997年以降のメタ分析に対する確
認または反論を目的としたこの研究(1)では、頭部外傷に対しステロイドを使用した(30年に
わたる慣習)場合に死亡率が1~2%低下していることが示された。この研究では頭部外傷患者
10.008例を高用量ステロイド群またはプラセボ群に無作為に割り当てた。この研究をもとに、さ
らに2件の重要な論文が発表された(18,19)。彼らはプラセボ群に比べステロイド投与群にお
〆癒、
/侭蕪、
15
いて、短期の致死率および長期の致死率・後遺症の割合(獣医療では安楽死を示唆する)がより
高いことを裏付ける十分なエビデンスを示した。これに加え、獣医療における研究では、頭部外
傷の犬や猫に高血糖症が関連しており、高血糖の程度が頭部外傷の重症度に関連していることが
示唆された。高血糖の程度は頭部外傷の犬と猫の転帰に関連性は認められなかったが、高血糖は
神経損傷を悪化させる可能性があることから、頭部外傷患者では医原性高血糖を避ける必要があ
る(56)。
4.7.2.脊椎損傷:外傷性または椎間板疾患
ヒト医療の文献では、損傷の8時間以内(理想的には3時間以内)にステロイド投与を開始した
場合、ステロイドが神経の回復に有用としているようである。損傷後8時間以上経過している場
合は、ステロイド投与は悪影響のほうが大きくなる。しかしGCのの影響は千差万別であり、評
価項目を注意深く検討し、統計的に有意な結果が臨床的な有用性を示すとは限らないことを忘れ
てはならない。獣医の視点では、動物が自力歩行でき、随意排尿できることが重要となる。獣医
にとって指や手を動かせるなどの改善は臨床的意義がない。これらはヒトでの研究で注目すべき
評価項目である。この差は基本的に車椅子を操縦する患者で問題となるもので、我々獣医にとっ
てのゴールとなる歩行については差が見られなかった。またNASCIS-2およびNASCIS-3のいずれ
〆翻MR
侭撫賦
についても統計、無作為化および臨床的評価項目に重大な懸念があり、この研究ではステロイド
について統計学的有意性のみを示唆し、臨床的有意性は示していないようである。(42)。
動物医療における研究はどうであろうか?椎間板疾患を外科的に治療したダックスフントにお
けるコハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム(MPSS)治療の合併症に関する研究では、MPSS
投与犬では、(他のGCと比較しても)臨床的に明らかな術後の消化管合併症の発生率が高く、
消化管保護剤の使用量や入院にかかった費用も多かった(9)。歩行不能のハンセンI型椎間板
ヘルニア症例(308例)の転帰および予後因子に関する研究では、ステロイドの使用は(術前、
術後のいずれについても)歩行可能になるまでの時間に影響しなかった(53)。急性胸腰椎椎間
板疾患に対して片側椎弓切除術を行った後、MPSSを投与しなかった歩行不能な犬51匹の転帰
に関する前向き研究を行った(16)。手術前は全症例が歩行不能であり(対麻痩26、不全対麻
庫25例)、98%に嬉痛が見られた。歩行不能の小型犬では片側椎弓切除術が歩行の回復に非常
に有効であり、MPSSを手術に加えて追加投与する必要性はないようである。(16)。最近の後
ろ向き研究では、手術で椎間板ヘルニアを確認した犬161例にデキサメサゾンを投与した場合と、
他のGC(プレドニゾロンまたはメチルプレドニゾロン)およびGCを投与しない場合で比較し
ている(35)。その結果デキサメサゾンは他のGC投与群およびGC不投与群と比較し最も成績
が悪かった。興味深いことに、転帰に差異は認められなかったため、ここでもGC使用のリスク
が有用性を上回っていると思われる。これらの所見は、高用量のステロイドには重度の副反応が
伴うこと、事態を悪化させる可能性が示された。(‘Ipr”””,〃o〃〃ocere’,「まず害を与えないこ
と」)したがって、急性脊椎損傷に対するGCの使用は妥当とはいえない。
脊椎に痩痛があり椎間板疾患が診断または疑われるものの、明らかな神経障害が認められない犬
では、抗炎症用量のプレドニゾン0.5~1mg/kgBmで短期間(1~2週間)治療した後、適宜漸
減することができる。しかし6~8週間のケージレストが最も重要な治療であることを飼主に指
導することが大切である。
4.7.3.痩譲および頭蓋内腫癌
顕著な脳浮腫を伴う頭蓋内腫傷の犬や猫において、抗炎症用量のステロイド剤が奏功することが
ある。この方法は手術不可能な病変が確認された場合には特に有用である。しかしGCがてんか
ん重積症の治療に効果があるというエビデンスはなく、高血糖症などの重大な副反応を生じる可
能性もある。
4.8.敗血症および敗血症性ショック
4.8.1.ヒトにおける医療
1970年代の終わりから1980年代の初めにかけて、敗血症性ショックの治療に高用量のGCが使
われ始めた。メチルプレドニゾロンに代表されるGCの用量は一般に30mg/kgと高く、投与期間
16
は1日と短かった。この時期には、救命医療の分野で厳密に計画された臨床試験が実施されるよ
うになり、短期の高用量メチルプレドニゾロン投与は敗血症死亡率を低下させず、むしろ消化管
出血など重大な副反応と相関性が示唆された。敗血症性ショックの初期におけるGCの高用量、
単回投与の有用性に関する臨床試験によれば、このような処置が死亡率を改善する可能性は低い
と結論づけている。(26,32)。
相対的副腎機能不全(relativeadrenalinsufficiency,RAI)が敗血症性ショックの患者で報告さ
れている。この種の副腎機能不全患者は古典的な副腎機能低下症(アジソン病)で見られるよう
な絶対的な副腎機能不全は認められない。コルチゾールは産生されているものの、その分泌量が
疾患の程度に相応していない。RAIは昇圧剤抵抗性低血圧および死亡と関連している。古典的な
副腎機能低下症とは異なり、血清コルチゾール濃度がいつも低いというわけでもないことから、
この論文では相対的副腎機能不全(RAI)と報告している(4)。RAIの病態生理学は不明である。
重症患者に見られる副腎機能不全は、視床下部または下垂体の機能不全に起因する可能性もある
(続発性副腎機能不全)。また、GC輸送の変化またはGC受容体の親和性低下が何らかの役割を
果たしていると考えられる。(47)。この疾患の根底には多くの因子が関与し、単独または複数
の病態生理学的メカニズムが関わっている可能性がある。Ⅱ-1、IL-6、TNF-a等の炎症性サイト
カインによる視床下部・下垂体・副腎皮質(1浬A)軸の抑制が関わっているとする説がある(3,
8,26,47)。敗血症患者の副腎機能不全は、副腎における出血や微小血管血栓症とも関連して
いる。エンドトキシンもコルチゾールのGC受容体の親和性を低下させ、受容体のダウンレギュ
レーシヨンを引き起こす(47)。
RAIを診断する最良の方法は見つかっていない。ヒトでは、コシントロピン250mg投与後の血清
コルチゾール濃度を基礎血清コルチゾール濃度と比較する標準的ACTH刺激試験が最も一般的な
診断法である。ACTH刺激後の血清コルチゾール濃度から基礎血清コルチゾール濃度を引いた値
をデルタコルチゾールとし、250,mol/L以下(<9mg/dL)ではヒトの昇圧剤抵抗性低血圧および
死亡と相関が見られる(3,4)。重症患者における、A軸の機能障害を検出する方法として上記
のほかに、基礎コルチゾール濃度、ACTH刺激後コルチゾール濃度、内因性AC、濃度と基礎コ
ルチゾール濃度の比、およびこれらの組み合わせがある(3,20)。遊離型コルチゾールおよび
コルチゾール結合タンパク質(CBG)も、特に低タンパク血症患者で指標とすることができる
(26,27)。また、より生理学的に近いコシントロピンを成人1人当たり1mgの用量でACTH刺
激試験に用いる方法が検討されたが、まだ検査法として確立されていない(2)。
2002年、Annanらはフランスの集中治療室(19施設)で治療を受けた299人の敗血症性ショック患
者を対象に、無作為の二重盲検プラセボコントロール試験を実施した。(5)。標準的な250mg
のAC、刺激試験を行い、患者の77%にRAIが認められた(基礎値および刺激後のデルタコルチ
ゾール濃度が0.25,mol/L未満(<9仏g/dL))。患者はヒドロコルチゾン(50mglVQm)投与
群およびフルドロコルチゾン(50mgPOSID)投与群、プラセボ群に分けられた。RAIが認めら
れなかった患者では、プラセボ群と治療群に死亡率に有意差は認められなかった。RAIが診断さ
れた患者では昇圧剤を中止できるまでの日数が、プラセボ群で平均10日、治療群で平均7日間で
あった。GCの副反応については2群間で差は認められなかった。生存率の改善は輸液療法および
昇圧剤による蘇生に反応せず、ACTH投与後にも血清コルチゾール値が適切に上昇しない患者で
のみ認められたが、この研究以来、ヒドロコルチゾン(ストレス用量、約300mgQm)が敗血症
性ショックの患者において広く用いられるようになった。(37)
2008年には、CORTICUS(55)が多施設の無作為二重盲検プラセボコントロール試験をJoumal
ofNewEnglandMedicineに発表している。患者251人にヒドロコルチゾン50mgを、248人にプラセ
ボをそれぞれ6時間毎に5日間静脈内投与した。その後6日間にわたって用量を漸減した。ヒドロ
コルチゾン投与群では、プラセボ群と比較してショックの回復が速やかであった。しかし、新規
の敗血症および敗血症性ショック等の重複感染例は増加した。ヒドロコルチゾンの投与により、
ショックから回復した患者群ではその回復が早まったものの、生存率およびショックからの回復
は、患者全体においてもACTHに無反応の患者においても、改善を認めなかった。(55)。した
がってCORTICUS試験の結果では、副腎皮質の反応性とヒドロコルチゾンの血圧改善効果との関
係に疑問が生じている。(43)。
これら2試験の試験結果の大きな違いは、母集団の疾患重症度の差に一部起因している可能性が
〆f熟、
/雨’㈹
17
高い。Annaneらの被験者はCORTICUSに比べ疾患の重症度が高かった。(5)。Annaneら
(2002)の試験は敗血症性ショック発症後8時間以内の患者を対象にしており、一方CORTICUS
の試験ではショックの発症後72時間以内の患者を対象としている。敗血症性ショック発症後72時
間生存した患者は、概してその後の予後も良い傾向がある。対象患者を選ぶ基準の違いから、ヒ
ドロコルチゾンが有益とならない安定した患者群が試験の対象となった可能性がある。また
CORnCUS試験はSurvivingSepsisCampaignGuidelines(敗血症管理のガイドライン)の初版発行
後に実施された(21)。このガイドラインでは、血圧管理のため適切な輸液療法および昇圧剤投
与が必要となる敗血症性ショック患者に対してヒドロコルチゾンの使用を推奨している。したが
って多くの医者がより重篤な患者群を対象から除外した可能性がある。Annaneらの研究ではフ
ルドロコルチゾンの併用が血管容量を増加し治療効果を増大させ、生存率を上昇させた可能性が
ある。これらの点から、I悪A軸の機能とは無関係に低用量上ドロコルチゾン投与に反応する昇圧
剤抵抗性の低血圧患者の存在が示唆される。しかしCORTTCUSではRAIの適切な診断を欠いてい
たことから、ヒドロコルチゾン反応性低血圧は異なる病態である可能性がある(5,43,55)。
最後に、2008年のメタ分析では、ステロイドは死亡率には影響しないがショックからの回復を早
めると結論された。(50)。
2008年のSurvivingSepsisCampaignでは、敗血症性シヨックにおけるGCの使用について以下のよ
認照へ
.J愈験、
うな指針が出されている(22)。
・成人の敗血症性ショックでは、適切な輸液蘇生および昇圧剤に対して無反応性の低血圧である
場合はヒドロコルチゾンの静脈投与を考慮するccノ。
oヒドロコルチゾンを投与すべき成人敗血症ショック患者のを特定する目的でACTH刺激試験を
行うことは推奨されない。(2Bノ。
・デキサメサゾンよりもヒドロコルチゾンのほうが望ましい(2Bノ.
。上ドロコルチゾン投与後も十分なMC活性が見られない場合は、フルドロコルチゾン(50U9,
POS、)を用いてもよい。Cノ。フルドロコルチゾンは、ヒドロコルチゾンを使用した後のオ
プションである。
・昇圧剤が必要でない状態になってからステロイド療法から離脱させる(2,ノ。
。上ドロコルチゾンの用量は300mg/day以下とするべきである。(1W。
・ショックを呈さない敗血症では、内分泌疾患またはGC投与のヒストリーから妥当と考えられ
ない限り、治療にGCを使用しない‘Dノ。
ガイドラインではエビデンスのクオリティーを「高い」(A)から「非常に低い」(D)に格付
けした。GRADEシステムにより推奨度を決定した。強い推奨[l]は望ましい効果が望ましくな
い効果およびリスクを明らかに上回る(または下回る)ことを意味する。弱い推奨[2]とは望
ましい効果と望ましくない効果の相殺の程度が明確でないことを意味する。「強い」および「弱
い」という等級は、臨床上の重要性を意味するものであり、エビデンスの質を意味するものでは
ない。
4.8.2.動物医療
最近の研究でRAIが敗血症および重症の動物で診断されたが、RAIの犬や猫に低用量上ドロコル
チゾン治療が奏功するかどうかについては明確に記述されていない。
最初の前向き臨床研究ではRAIは動物医療において一般的ではないと仮定している(48)。集中
治療中の犬20頭について、コルチゾール基礎濃度の測定し、その後ACTH50mgによる標準的刺
激試験を行い、コルチゾール濃度および血清ACTH濃度を測定した。いずれも退院または死亡時
まで1日1回継続的に測定した。急性腹症、腫傷、敗血症、腎不全、呼吸器系疾患、糖尿病性ケト
アシドーシス、うっ血性心不全等の様々な疾患の犬が対象となった。基礎コルチゾール濃度は犬
の37%で上昇したが、残りの犬では参照範囲内であった。ACTH刺激後のコルチゾール濃度は、
犬の90%が参照範囲内、10%が高値であった。内因性ACTH濃度は犬の54%が正常、35%が低値、
12%が高値であった。生存した犬と死亡した犬で比較しても、基礎コルチゾール濃度、ACTH刺
激所見およびACTH濃度に有意差は認められなかった。また内因性ACTHとコルチゾール濃度に
も相関性は認められなかった。この研究はサンプル量が少なく、対象の疾患が多様であり、低血
圧や積極的な輸液・昇圧療法に関する記述がないという制限があった。
Prittieら(2003)も重症の猫20頭に関する研究(未発表)を行っている(49)。敗血症の猫に副
腎機能不全は認められなかった。
18
ある未発表の後ろ向き研究では、犬42頭中4頭(9.5%)でRAIが診断された(54)。
ある前向き研究では敗血症の犬33頭が検討されている(15)。コシントロピン250mgを筋肉内投
与し、投与前に血清コルチゾールおよび内因性ACTH濃度を、投与後1時間に血清コルチゾール
濃度を測定した。△コルチゾール濃度を測定したところ、低血圧は△コルチゾール値の低下と
関連性が見られた。△コルチゾールのカットオフ値83,mol/L(3.0mg/dL)は低血圧および退院
までの生存率および28日間生存率を予測する指標として最も精度が高かった。△コルチゾール濃
度が83,mol/L未満(<3mg/dL)の犬の死亡率は、△コルチゾール濃度が83,mol/Lを超える(>
3.0mg/dL)犬の4.1倍であった。ACTH刺激後の△コルチゾール濃度が83,mol/L未満(<3.0
mg/dL)の場合、敗血症の犬における全身性低血圧および生存率の低下と相関が認められた
(15)。
2008年の前向き研究では敗血症、重度外傷および胃拡張捻転(GDV)の重症患犬における下垂
体・副腎機能の評価を目的とした(40)。研究に供された犬31頭は急性重症疾患の発症後48時間
以内に入院した。集中治療室に搬送されてから24時間以内に基礎血清コルチゾール濃度、ACTH
刺激後コルチゾール濃度および基礎ACTH濃度を測定した。各犬の△コルチゾール値を算出した
ところ、犬31頭中17頭(55%)は副腎または下垂体の機能不全を示唆する生化学的異常が一つ以
上認められた。ACTH刺激に対する低反応性が認められた犬は1例(3%)のみであった。△コル
チゾール値が83,mol/L以下の犬は83,mol/Lを超える犬と比較し、昇圧剤を投与する確率が5.7倍
高かった(40)。
PeytonおよびBurkitt(2009)は犬の自然発生的敗血症性ショックにおけるヒドロコルチゾン反応
性低血圧および一過性のRAIの最初の症例報告を行った(43)。この犬は誤礁性肺炎を患い、昇
圧剤抵抗性低血圧を伴う敗血症性ショックを発症した。標準的ACTH刺激試験の結果、RAIを示
唆するコルチゾール反応の鈍化が認められた。ヒドロコルチゾン投与後2時間以内にショックが
回復し、その後の8時間で昇圧剤の投薬を中止できた。犬は回復し退院し、退院後1カ月後に行
ったACTH刺激試験ではRAIの消失と一致する副腎皮質の正常な反応が確認された(43)。
敗血症および敗血症性ショックにおけるRAIに関する動物の研究はほとんどないが、積極的な輸
液・昇圧剤治療にもかかわらず血圧が低いままの敗血症性ショック動物ではRAIを疑うべきであ
る。著者のほとんどはACTH刺激試験(250mg)を推奨している。△コルチゾール値のカットオ
フ値は83,mol/L(3.0mg/dL)である。PeytonおよびBurkitt(2009)はヒドロコルチゾン0.5mg/kg
IVQID(2mg/kg/day)を推奨している(43)。この上ドロコルチゾンの用量はプレドニゾンの約
0.5mg/kg/dayに相当する(25)。ヒトで用いられるヒドロコルチゾンの用量は2.9~4.3mg/kg/day
(300mg/day)であり、生理的用量、ストレス用量、補充用量または低用量と呼ばれる(5,6,
12)。ヒドロコルチゾンの投与は定速注入よりも投与が容易な間欠的ボーラス投与が便利で、投
薬中止には6日以上かけることが望ましい。退院時にはGC投与を必要としない状態とする。敗血
症性ショックが消失する前にヒドロコルチゾンを離脱すると血行動態を悪化させるため、GC補
充療法は患者が安定し、改善が認められてから減薬する(36)。犬では、自分から食べ始めるよ
うになった時、あるいは退院予定日の数日前にGCからの離脱を考えるのが妥当である(43)。
RAIが疑われる患者にはGCのストレス用量を、ACTH刺激試験後に投与する。
GC補充療法が有益かどうかを決めるためには更なる研究が必要である。
4.9.他の種類のショックにおける相対的副腎機能不全(RAI)
4.9.1.ヒト医療
RAIは敗血症性ショック患者で十分に示された疾患であるが、他の重症疾患でも起こることが最
近の研究で明らかにされている。RAIは外傷、腫傷、炎症または感染などの病態で検討されてい
る(51)。GCは急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の初期でRAIを伴う場合に、有病率および死亡率
を改善した。RAIはARDSおよび敗血症性ショックの患者では十分立証されている(6,51)。あ
る研究では、出血性ショックおよび外傷患者では47%にRAIが認められた(28)。
ある外傷性脳損傷の研究ではRAI発生率が53%であり、そのメカニズムとして、A軸の血流低下
が示唆されている(17)。
RAIは人工呼吸器の患者でも報告されている。(30)
RAIは重度の肝疾患および肝移植後にGCを投与しなかった患者の72%で診断されている(39)。
ある研究では壊死性騨炎の患者でRAIの可能性を示唆している。(41)。
/鰯?、
/雨添
19
4.9.2.動物医療
リンパ腫の猫に関する1999年の未発表研究では、ACTH刺激試験に対する反応が10頭中9頭で正
常以下であった(24)。
Prittieら(2003)の重症猫20頭に関する未発表研究は、腫蕩性疾患の猫の△コルチゾール値が低
値であることを明らかにした(49)。
2005年の未発表研究では、リンパ腫および非血液性腫揚の犬のI悪A軸が評価されている(11)。
リンパ腫の犬の20%、および非血液性腫揚の犬の19%はACTH刺激に無反応であった。
Durkanら(2007)は多発性外傷の猫の1例で、輸液療法および昇圧剤治療に反応しない低血圧を
伴うRAIを示唆している。猫は最終的に回復し、GC補充療法を中止した(23)。
Martinらによる2008年の前向き研究では、敗血症、重度の外傷、GDVなどの様々な重篤疾患の
犬で、RAIを示唆する生化学所見を示した。また、ACTH投与に対する過剰反応は稀であった
(40)。
4.10.動物医療におけるRAIのまとめ
RAIは敗血症、敗血症性ショック、外傷、腫傷および炎症性反応性症候群の動物で報告または疑
われている。動物の救急医療におけるRAIの役割を明らかにするには、さらなる研究が必要であ
,’2撫鳥
,霞諦Bh
る。特に人工呼吸器患者、出血または敗血症性ショック患者、外傷後の患者、SIRSや肝疾患また
は騨炎の患者、十分な輸液療法および昇圧剤治療にもかかわらず低血圧の患者等におけるRAIの
発生を中心に検討する必要がある。ヒトおよび動物医療におけるRAIの診断は意見が大きく分か
れるところであるが、診断には通常基礎コルチゾールの測定およびACTH刺激試験が必要である。
RAIを診断する最も正確な方法を決定するにはさらなる研究が必要である。積極的な輸液および
昇圧剤治療でも血圧が低いままの重症患者ではRAIを考慮する必要がある。これらの動物には
ACTH刺激試験を行い、ストレス用量のGCを投与する。プレドニゾン0.4mg/kg/dayまたはメチル
プレドニゾロンが使用できる(26)。デキサメサゾンは現在のところ推奨されない。ミネラルコ
ルチコイド(フルドロコルチゾン)の使用に関する情報は知られていない。高用量のステロイド
(メチルプレドニゾロン30mg/kg/day)は有病率および死亡率に悪影響を及ぼすことが示されて
いる。
4.11.その他の適応症
4.11.1.高カルシウム血症
GCは消化管からのカルシウム吸収を低下させ、腎臓のカルシウム排池を促す。可能であれば
(血清総カルシウム濃度ではなく)血清イオン化カルシウム濃度を用いて診断する。高カルシウ
ム血症によると思われる臨床症状(高窒素血症、虚弱、胃腸障害、振戦等)を呈す患者は、デキ
サメサゾン0.1~0.22mg/kgまたはプレドニゾロンl~2.2mg/kgBIDにより治療することができる。
高カルシウム血症に対するその他の適切な治療も実施する(可能であれば基礎疾患の治療、輸液
療法、フロセミド)(1,10,25)。
4.11.2.インスリノーマ
GCはグリコーゲン分解および末梢インスリン抵抗性を誘発する。したがって、インスリノーマ
による低血糖症患者の血中グルコース濃度の維持にしばしば使用される。最も一般的な用量は経
口または注射用プレドニゾロン0.25mg/kgBIDであり、奏功するまで用量を漸増する。ただし治
療目的は臨床症状の管理であり、正常血糖の維持ではない(14,25).
4.11.3.もうひとつの適応の可能性
猫の尿道閉塞に続発する急性尿道炎の浮腫に対し、抗炎症性用量のデキサメサゾン(0.1~0.2
mg/kg)またはプレドニゾロン(0.5~2mg/kg)単回投与が一般的に用いられるが、その有益性の
具体的なエビデンスは得られていない。この病態では高用量は適応とならない(7)。
適切な診断検査および治療計画を行わずに、食欲を刺激するためにステロイドを使用するべきで
はない(14,25)。
5.ステロイドの副反応
GCの副反応は膨大であり、ここに全てを記述することはできない。生命を脅かす可能性のある
20
副反応としては、免疫抑制および感染性の増加、創傷治癒の遅延、消化管漬傷および穿孔、血栓
症、騨炎、糖尿病様症状を伴う医原性高血糖等がある。副反応の程度は概して用量に依存するが、
犬や猫はGCに対する反応に顕著な固体差があり、抗炎症性用量のステロイドでさえ合併症を引
き起こす動物もいる。概して犬は猫に比べてGCの作用(良くも悪くも)に対する感受性が高い
傾向がある(10,14,25,45)。
6.GCの使用が禁忌となる疾患
GCは糖尿病、騨臓炎、ほとんどの感染症、消化管潰傷(炎症性腸疾患に続発する潰傷を除く)、
NSAIDsを使用している動物には禁忌である。角膜裂傷または潰傷に点眼用ステロイドは一般的
に禁忌である。頭部外傷、脊髄損傷、出血性ショック、血液量減少性ショックまたは敗血症の動
物における高用量GCの使用を支持する臨床的証拠は乏しい。十分に立証されたステロイドの副
反応を考慮すると、より多くの情報が得られるまでこれらの疾患への使用は妥当でない(10,14,
25,45)